「宅建試験」に合格した経験から学んだこと
★セカンドキャリアに向けて「宅建資格」に挑戦
今回は、「宅建」の学習を通して、
自立して学ぶことの大切さと、
それが可能な時代になったことを実感したというお話をします。
私は、退職10年前ほどから、
セカンドキャリアに向けて、
宅地建物取引士、いわゆる宅建の資格取得を決意しました。
不動産関連の仕事を
視野に入れていた私にとって、
この資格は必要な資格でした。
しかし、いざ学習を始めようとした時、
最初の壁にぶつかりました。
「どうやって勉強すればいいのだろう?」

何から手を付ければいいのか
わからなかったのです。
書店には分厚い参考書が並び、
探せば、予備校や通信講座は
いくらでもありました。
迷いましたが、とりあえず、
予備校の体験コースを受講し
2週間通ってみることにしました。
★あまりにも苦痛だった「一斉授業」
結果、予備校は、
当時、教育行政で毎日遅くまで
働いていた私にとって時間的に無理だとわかりました。
しかし、それ以上に、
「一斉授業」という形式に、
馴染めませんでした。
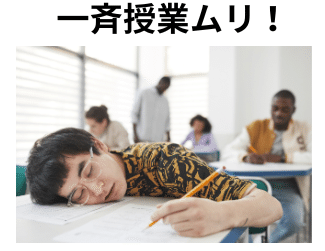
授業の進度は皆と同じ、
理解度に関わらず次々と
新しい単元に進んでいく。
個々のペースや
得意不得意は考慮されません。
何より、一方的に話を聞かさせる
ということに、
正直、苦痛を感じました。
今まで、教師として、
散々、一斉授業をしてきたのに、
授業を受ける立場になって
初めて、一斉授業を受ける生徒の
気持ちがわかったのです。
大いに反省しました。
★「独学」が可能な時代になった
ということで、
私は独学を選択しました。
学習の方法としては、
いきなり問題集に取り組むという
やり方をしました。
しかし、問題文そのものが難しすぎて、
何を問われているかすらわかりません。
ですので、
用語を一つ一つ調べていき
問題文を理解することから始めたのです。
これが一昔前なら、
その都度、参考書をめくりながら、
調べていたはずです。
これだと、
知りたいことにたどり着くのに
かなりの時間を要します。
しかし、今はネットがあります。
検索すればほとんどのことが
瞬時にわかります。

また、理解の浅い内容については
YouTubeなどの解説動画を
何度も見ました。
無料で質の高い動画が
多く公開されていて、かなり助けられました。
※その頃は、まだAIはありませんでしが
今ならAIを先生に見立てて質問もできます。
さらに、アプリや有料の
学習サイトを使って、
通勤時間や休憩時間など、
スキマ時間を有効活用しました。
それらを活用することで、
自分のペースで学習を進めることができたのです。
ITの進化が、「独学」を可能にしてくれていたのです。
これには感謝しました。
★「独学」の欠点
こういった方法で、
予備校に通うことなく学習を進めていったのですが、
結果は、2年連続の不合格。
もちろん、
忙しかったこともあり
絶対的な学習時間が不足していたこともあります。
しかし、敗因として、
一番大きかったのは、モチベーションの維持です。

宅建の試験は一年に一度しかありません。
2〜3ヶ月くらいなら
集中して学習できますが、
これが1年となると、
やる気を保ち続けるのは至難の業なのです。
これが、独学の最大のデメリットです。
予備校に通っていれば、
同じ目標に向かって頑張っている仲間がいます。
互いに励まし合いながら
切磋琢磨することもできます。
あと、講師や仲間から
「学び方を学ぶ」こともできます。
独学にはこういった
人間同士の関わり合いがありません。
★仲間の支えで「合格」
それを悟った私は、
SNSの学習コミュニティに参加しました。
そこでは、
同じように宅建試験を目指す仲間と
将来について語り合ったり、
互いの学び方のノウハウを
情報交換をしたりしたのです。
すると、ようやく3年目に
宅建に合格できたのです。
いやあ、嬉しかったですね。

宅建試験の合格は、
私にとって一つの大きな達成感でしたが、
それ以上に、
改めて「学ぶことの楽しさ」を
知りましたし、
学習にとって、
学び合う、支え合うことが
いかに大切なことかを学んだのです。
★学校に「自由進度学習」を取り入れる
この体験は、その後に校長になり、
学校を経営する際に、大いに役立ちました。
私は学校経営の方針を、
「自立した学習者」とし、
学校は「学び方」を
習得する場所であるという
考え方のもと、
主体的に学ぶ子どもの育成に
全力を注ぎました。
とくに、
算数と社会の授業で取り入れた
「自由進度学習」には大きな可能性を感じました。
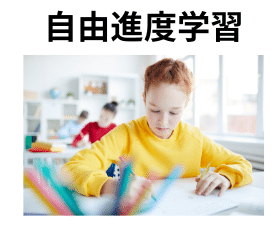
「自由進度学習」は、
学習者が自身のペースで
主体的に学ぶことができるので、
とくに、学力の高い子は
さらに学ぶスピードが速くなっただけでなく、
興味をもった事柄について
探究するようになっていきました。
学力的に課題のある子にとっては
最初のうちは戸惑いもありましたが、
教師や仲間からの
コーチングや励ましで、
自分の学び方に
目を向けるようになり
学び方において「自己調整」するようになっていきました。
積極的に仲間や先生に
気軽に相談できるようになったことも大きな変化でした。
「自立」とは、だれにも頼らず
自分だけで何かを達成する力ではありません。
必要なときには、だれかに
助けを求めることのできる力でもあるのです。
そして「学習者」というのは
勉強だけでなく、
目標の達成に向けて
試行錯誤しながら
精進していく人のことでもあるのです。
私の宅建への挑戦は、
まさに文科省の言う、
「学びの相似形」だったなと思っています。
教える側も、教えられる側と
同じように、
学び続けることが大事なのです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/


