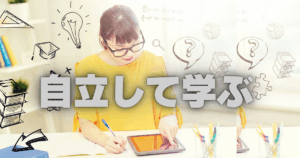学校でも議論している「校則」
★前回のつづき
前回は、学校の「校則」は、
その多くが社会的な要請・要望を
もとに作られているというお話をしました。
今回は、その続きで、
実は学校では「校則」について
たえず議論しており、
教職員間でも「校則」に対する
考え方は同じではないということを、
事例を通してお話しします。
★事例1 登校していても教室に入室していなければ「遅刻扱い」にする。(中学校)
教諭A 賛成
社会に出ると、時間管理は非常に重要になります。
単に学校に到着するだけでなく、
教室に入り、
授業を受ける準備を整えておく必要があります。

しかし、現状として、生徒は、
学校に所定の時刻までに
登校したものの、
校内でうろうろしたり、
部活動の朝練習したりといった
理由で教室への入室が遅れたりしています。
教室で、全員が揃っていない場合、
連絡などの時間が短縮されたりします。
「遅刻」の認識が
生徒によって異なっていては不公平が生じます。
教諭B 反対
教室への入室に
間に合わなかった場合は、
理由によっては注意すべきだが、
校内にいるわけだから、
遅刻と判定するのはおかしい。
一般社会のルールを
そのまま適応させてしまっては、
まだ発達段階の途上にある
生徒の育成にはならない。
ルールを厳格化させるのではなく、
教室への入室に間に合わなかった
生徒への指導のあり方を、
職員間で共有することの方が、
が教育的だと考えます。
★事例2 小学校ではシャープペンを禁止する。(小学校)
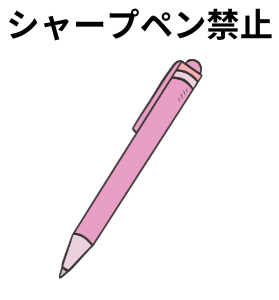
教諭A 賛成
文字をきれいに書くポイントは筆圧です。
鉛筆は、筆圧を意識しながら
書くのに適しています。
一方、シャープペンは芯が細いため、
筆圧のコントロールがまだ十分にできない小学生は芯を折ってしまうケースが多いです。
あと、シャープペンの先端は細く、
小学校では安全管理に細心の注意が必要になります。
とくに、低学年の子ども同士での
不注意な接触があった場合、
怪我につながる場合があります。
教諭B 反対
中学校ではシャープペンの使用が一般的です。
なのに、小学校で禁止することは、
中学校へのスムーズな移行を妨げる可能性があります。
そもそも、鉛筆にも
シャープペンにも
それぞれメリットとデメリットがあります。
一律に禁止するのではなく、
どちらを使うかの判断は家庭に任せるべきです。
それに、シャープペンの
安全性や機能は向上していて、
筆圧に対応したものも販売されています。
★事例3 タトゥーを入れている生徒がいる。調査を行い、「タトゥー禁止」をすべき(高校)

教諭A 賛成
タトゥーは、社会に少しずつ
受け入れられ、
一般的になりつつありますが、
まだまだ、拒否感をもっている方も方も多いです。
そんなタトゥーを学校が容認することは、
地域や保護者から支持を得られなくなります。
また、生徒が将来社会に出た際に
不利益を被ることも懸念されます。
卒業後、将来、自分の意志で
行うならいいですが、
高校生の間はまだ適切な判断ができるとは思えません。
教諭B 反対
一方的な禁止ではなく、
生徒との信頼関係を築きながら、
対話を通じて解決した方がいいと思います。
生徒には「表現の自由」があり、
自己決定が許されているのです。
まずは、多様な価値観を認め、
理解しようとする教育の理念を
大切にすべきです。
タトゥーを禁止したとしても、
生徒が抱える根本的な問題は解決されません。
禁止するのではなく、
生徒の抱える問題に寄り添い、
保護者とも話し合いながら考えていくべきです。
★厳しい「校則」の中で育ったからこそ
いかがですか。
学校は何でもかんでも
禁止しようとしているわけではなく、
まずは、子どもたちの
安心・安全を確保すること、
そして、社会性を育むことを
目指しているのだということを
おわかりいただけたでしょうか。
また、教師間でも、校則に対する
考え方や価値観が異なっていることに
お気づきになられたと思います。
おそらく日本の子どもたちは、
他国と比較しても、小中高と
厳しい「校則」のもとで学校生活を送っています。

それをどう考えるかです。
規律や集団生活のルールを
学びながら育つことで、
社会に出てからも秩序を守る意識や、
他者への配慮につながっており、
日本の治安の良さの
一因ともなっているかもしれません。
さらに、「製造業」や「サービス業」
においても、
お客様を思いやる姿勢や
丁寧な応対が世界から高く評価されています。
つまり、厳しい校則の背景には、
単なる規制ではなく、
社会性や礼儀、責任感を育むという教育的側面があり、
それが日本社会全体の
秩序と洗練さにつながっているのではないかと思うのです。
これはあくまで私の感想ですが。
★生徒にも「校則」の策定に関わらせる
そうは言っても、
「校則」については課題もあります。
その一つが、学校から
生徒に対する一方的な
「押しつけ」になってしまっていることです。
これからの時代の学校では、
生徒の主体性を育むためにも、
「校則」の策定や改定に生徒自身が関わることが求められます。

自分たちの学校のルールを考え、
議論し、決定する過程は、
主権者教育としても重要であり、
将来、社会の一員として
責任ある行動をとる力を養います。
教師が一方的に決めるのではなく、
生徒とともに校則を見直すことが、
民主的な学校づくりの第一歩となるのです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/