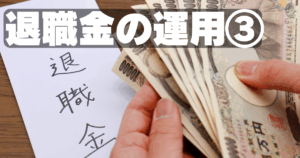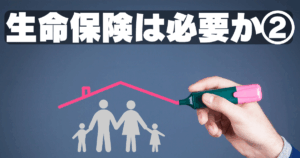生命保険への加入①~資産形成の鬼門~
★「手堅さ」があだになっている
さて、今回から民間の保険について
何回かに分けて
シリーズでお話ししていきたいと思います。
なぜ、保険の話かと言いますと、
まず、資産形成を考える上で、
見直さなくてはならなのが、
「家計」です。
そして、教職員の場合、
民間の保険料が家計のかなりの
割合を占めていることが多いからです。
教職員の場合に限らず、
公務員になられる方々の
特徴ともいえるのが「手堅さ」です。
無駄な支出はしませんし、
借りたものは必ず返します。
大きな賭けもしませんが、
儲けは小さくても
しっかり取りに行きます。
合理的に物事を考える方が多く、
慎重に物事を進めていくことのできる方々が多いのです。
そんな教職員の皆さんが
なぜか民間の保険に対しては
かなり無防備なんです。
かなりの保険料を支払っているのにですよ。
不思議ですよね。
しかし、一見矛盾しているようですが、
そこには、
「何かあった時のために」
という「リスク回避」の思考が働いています。
「手堅い」性格が、
「何かあった時のために」
ということにつながり、
それが、保険に加入となり、
そして、高い保険料でも仕方がない、
となっている構図なのです。
この手堅さと、リスク回避思考は
悪いことではありません。
むしろ大きな挫折や
失敗はないでしょう。
それが、金融機関や
民間の保険会社からすると、
教職員の方々に対する
絶大な「信用力」に
つながっているのは確かです。
とはいえ、
ここには問題があります。
高額な保険料を払い続けていると、
資産形成は難しいのです。
なので、この民間の保険料を
最小限に抑えていくことが
資産形成の第一歩となります。
★世界に感たる日本の保険制度
民間の保険の是非を問うためには
まずは、公的な保険について
理解する必要があります。
そもそもですが、
日本の公的な保険は、
世界的に見ても、かなり優れた制度です。
いつでも自由にどの医療機関でも
公的保険を使った医療を受けられますし、
負担の少ない医療費で
高度な医療が提供されています。
そして、そこには、
公費も投入されています。
しかも、その公的保険に
教職員なら平均的に
月5万円前後の保険料を支払っているのです。
(かなりざっくりとした計算ですが)
こういった公的な保険に
守られていながら、
さらに追加として、
高額ともいえる保険料を支払っているのです。
たしかに、この公的な保険料で
賄えないくらいの医療費を
支払わなくてはならないこともありますし、
公的な保険ではカバーしていないものもあります。
しかし、こういった不測の事態に
対応するための対策は
何も民間の保険に加入しかないということではありません。
ということで、
このシリーズでは、「資産形成」を進めるために、
民間の保険について、
加入すべきものと、
そうでないものについて考えていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/