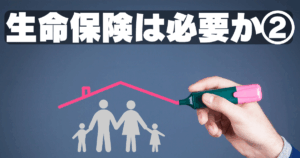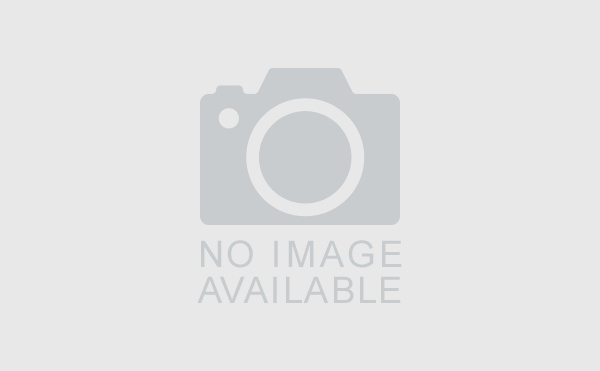生命保険への加入③~こんなに守られている教職員~
★「公立学校共済組合」に守られている教職員
資産形成を進めていくうえで、
民間の保険が
家計の固定費として立ちはだかる状況について、
いかに改善していけばいいのか、
についてシリーズでお話ししています。
今回は、
とくに第三分野の「医療保険」について
考えてみます。
医療保険には、
「公的保険」と「民間の保険」
の2つに分類されますが、
皆保険制度である日本においては、
公的保険は、「加入しない」という
選択肢はありません。
そして、この皆保険制度は、
「被用者保険」
「国民健康保険」
「後期高齢者医療制度」
の3つの種類があります。
このうち、
公務員や会社員は被用者保険の対象者となり、
公立の教職員の場合、
公務員ですから、
「被用者保険」の対象となります。
そして、公立の教職員は、
「公立学校共済組合」に
加入することになります。
実はこの「公立学校共済組合」の保険は
大変優れたものなんです。
たとえば、
医療費の月の窓口負担が、
高額になった場合は、
高額療養費制度が適用されますが、
共済組合には、
高額療養費制度が適用された後も、
自己負担額が一定額を超えている場合、
その超えた部分が「一部負担金払戻金」や
「家族療養費附加金」として
自動的に払い戻されます。
あと、公務外の病気やケガで
勤務できない場合、
最長1年6ヶ月間、給料の一部が
「傷病手当金」として支給されます。
国民健康保険には
この傷病手当金の制度はありません。
ですので、
自営業者やフリーランスの方などは、
「就業不能保険」などで、その事態に備える必要があります。
しかし、公立学校の教職員の方は、
このような保険に加入する必要はありません。
さらに、共済組合は、
人間ドックや健康診断の補助や、
出産費附加金、育児休業手当金、
休業給付など、国民健康保険では
受けられない福利厚生サービスがあるのです。
★なぜ医療保険に入ってしまうのか
これだけ手厚い保険に守られていながら、
なぜ、民間の医療保険に入るのか
ということですが、
まず、そもそも
公立の教職員がこれだけ
手厚い保険で守られていることを知らないのです。
そんな中、保険の営業の方に
「万が一のことがあった時、ご家族は路頭に迷いませんか?」
「もしも病気になって働けなくなったら、収入はどうなりますか?」
「お子様の教育費、公立だけでなく私立も視野に入れると、いくら必要かご存知ですか?」
「老後2,000万円問題は、他人事ではありませんよ。」
なんて不安をあおられる言葉を投げかけられたら、
それは加入しますよ。
しかし、これらのリスクへの対応は
公立学校共済組合の保険で解決できるものばかりです。
とくに医療分野のリスクについては
ほとんど心配する必要がありません。
ですので、民間の医療保険については
その必要性をよく吟味してほしいのです。
★森永卓郎さんの治療費
話は飛んでしまいますが、
ご存知の方も多いと思いますが、
お亡くなりになられた、
経済アナリストの森永卓郎さんは、
がん治療に数千万円の自己負担をされたとお話しされていました。
その話を聞いて、
「高額療養費制度」は
機能しなかったのかと思われた方も多かったと思います。
それについては、森永さんは、
医療機関の勧める治療法ではなく、
「自由診療」に属する治療法を
選択されたことが自己負担が多くなった理由なのです。
具体的には、「血液免疫療法」という
公的医療保険の適用外の治療法を行ったことで、
全額自己負担となったということなんです。
では、森永さんは、
その自己負担分の治療費を
どのように捻出したかということですが、
最も大きな資金源は、
ご自身で築き上げてきた預貯金や金融資産です。
億単位の資産があったことを
示唆する発言もされており、
その一部を治療費に充てることができたと考えられます。
また、それだけではなく、
治療中も体調が許す範囲で
テレビ出演や講演活動、執筆などを継続されていました。
これらの継続的な収入も、
日々の生活費や治療費の一部に充てられたと考えられます。
森永さんが特に強調されていたのは、
「(自分は)お金があったから
自由診療を受けられた。
お金がなかったらこの治療は受けられなかった」
という点です。
これは、最終的に頼れるものは
個人の経済力であるということを示唆する言葉です。
つまり、リスク回避として、
民間の保険だけでなく、
資産形成を進めることの
大切さを語っているのです。
なので、
私の意見もそうですが
保険に頼らない資産形成を進めることが最も大事なのです。
ということで今回は、
「医療保険」については、
日本は世界的にも優れた保険制度があり、
とくに教職員の場合は
心配はいらないということ、
ただし、資産形成を
こつこつと進めておくことが
大事であるというお話しでした。
次回は、個別の事例に合わせた
保険の考え方について
お話ししたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/