次期学習指導要領に期待すること
★そもそも学習指導要領とは
今回は、次期学習指導要領への
私からの要望についてお話しします。
この記事を読まれている方で、
教員以外の方にとって、
そもそも何なのかわからないかもしれません。
学習指導要領とは、
文部科学省が定める
教育課程(カリキュラム)の基準のことです。
幼稚園、小学校、
中学校、高等学校など、
各学校種や教科ごとに、
目標や大まかな内容が定められています。
たとえば、中学校の国語1年生では、
一週間に4時間、年間140時間、
授業を行うことになっています。
また、内容としては、話すこと・聞くこと
書くこと、読むことについて
学習します。
たかがカリキュラムと思わないでください。
このカリキュラムは、
日本においては、法的な拘束力があり、
教育に関連するあらゆるものに影響力を及ぼします。
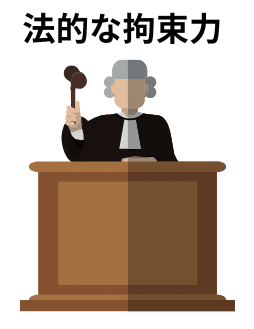
授業、教科書はもちろんのこと、
受験内容、問題集が
すべて学習指導要領に則っています。
つまり、学習指導要領は、
教育分野の「憲法」のようなものだと考えてください。
(たとえが適切かどうかはご容赦ください)
★「ゆとり」世代
この学習指導要領は、
10年に1度のサイクルで見直されています。
日本の教育における
「憲法」的なものだとはいえ、
教育という地味な分野ゆえに、
その改定について、
華々しく報道されることはありません。
それでも、過去には授業時数を大きく減らし、
「ゆとり教育」を目玉に改定が
行われたことは覚えている方もいるかもしれません。
結果、学力が下がったと
大騒ぎになりましたし、
その頃に教育を受けた方々を
「ゆとり世代」と評したりしますよ。

総合的な学習や小学校英語、
プログラミング教育といった
内容についても話題になったりしました。
地味でありながらも、
それくらいの影響力をもっているのが
この学習指導要領なのです。
その学習指導要領が、
2027年(令和9年)に改定されます。
その改訂に向けて、
協議が始まっているのです。
★で、実際、日本の教育はどうなの
学習指導要領は、
教育の世界では「憲法」くらいの
影響力があるとはいえ、
その成果はどうなの、
ということです。
とりあええず、
文科省がどう考えている成果について
まとめられていますので、
https://search.app/7qZS3UGv6QUtoKCR8
次期学習指導要領では、指導事項の選択と配列の最適化、構造化が必要【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#04】 | みんなの教育技術2024年12月25日、学習指導要領の改訂に向けた諮問文が示されましたが、それを受け、25年1月30日に中央教育審議会教育search.app
その内容に、私の意見を加えて
お話していきます。
まず一つ目。
◆学力の地域間格差が縮小傾向
学習指導要領の存在意義はここにあります。
文科省も「学習指導要領は、
全国のどの地域で教育を受けても、
一定の水準の教育を受けられるようにするためのもの」
と言っています。
沖縄県や北海道で教育を受けても、
東京、大阪、福岡で教育を受けたとしても、
ある一定の学力を身につけることができる。
私的にはここが日本の教育制度
の一番素晴らしいところだと
思っています。
世界一教育格差のない国が、
日本だと思ってます。

明確なデータは手元にありませんが。
もし、研究データ等があれば
教えてください。
2つ目の成果として、
◆OECDのPISA調査で高位層の割合が増え、低位層の割合が減った
OECDとは、経済協力開発機構の略で
世界38か国が加盟しています。
いわゆる先進国といわれる国々です。
そのOECDが実施する
学力調査において、
日本はほぼすべての領域でトップです。
それだけでもすごいのですが、
それに加えて、上位層が増えていて、
下位層の割合が少なくなっているというのです。
世界のモデルとなる
教育立国といってもいいでしょう。
★課題点はあるの?
これだけ成果が出ているのですから、
課題点なんてあるんですか、
と言いたくなりますよね。
そこで、元教員である
私なりの課題点を述べさせていただきます。
現行の学習指導要領は素晴らしい。
だからこそ成果が出ている。
なので言うことはありません。
しかし、あえて言うのならば、
わかりやすい表記を心がけてほしい、
ということです。
抽象的な言葉が多すぎるのです。
たとえば、次のような言葉。
「主体的・対話的な深い学び」
「学びに向かう力、人間性」
「社会に開かれた教育課程」
「カリキュラム・マネジメント」
わかりそうでわからないのです。
抽象的過ぎて、わかりそうで
わからない。
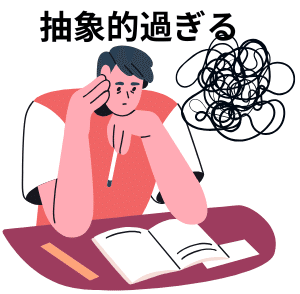
これらのことについて、
自信をもって説明できる教員は
ほとんどいないと言っていいでしょう。
なので、書店には
多くの解説本が並んでいます。
解説本を読まなくては
理解ができないほど難解なのです。
多くの教員は素直で
勉強熱心です。
なので、学習指導要領が難解でも、
それを理解しようと頑張ります。
でも、それって、
先生方の熱意に頼りすぎです。
解説本を買わなくてもすむように、
もう少し、わかりやすく
表現してくれることを期待します。
そうすれば、学習指導要領に対する
理解と実践にブレがなくなり、
多くの実践事例が蓄積されることで、
さらに教育の質が向上し、
今以上に教育格差が
縮小していくのではと思っています。
みなさんはいかがお考えでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/


