学び続けるためには「言語化」が必要だというお話
★ブログ、メルマガ、なんでもやってます
今日は、何かを改善し
進化させていくためには、
「言語化」が必要だというお話をします。
私は現在61歳です。
60歳で退職をし、現在、教師の資産形成、
セカンドキャリアについての支援事業をしています。
事業を進めていく上では、
やはり発信することが
とても大事なタスクの一つになってくるわけですね。
なので、今は、毎日ブログ、
note、メルマガを書いています。
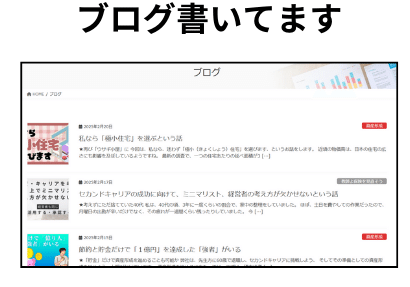
stand.fmで音声発信もしていますし、
細々とインスタやXもやってます。
Kindle本も3冊出しましたし、
まだアップできていませんが、
Udemyの動画も製作中です。
★IT環境に適応していくことの難しさ
こうした発信をするには、
さまざまなアプリやソフトを
使いこなす必要があります。
たとえば、CANVAというソフトや
マイスピというメルマガスタンドなどがそれです。
さすがにホームページ作成は
委託してますが、
ホームページ内のブログ作成は自分でやってます。
こう言うと、私がITやコンテンツ制作に
詳しい人なんだろうと
思われるかもしれませんが、とんでもありません。
今でも、Wordの書式は設定できませんし、
パワポでの動画作成も四苦八苦したりします。
なので、この1年間はかなりのストレスでした。
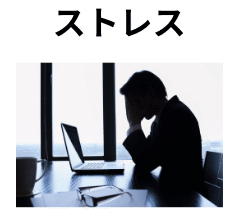
ただ、負けん気と根気はある方なので、
それこそトライアンドエラーの
繰り返しをしてきたということです。
発信をし始めて半年以上が過ぎましたが、
やっと慣れてきて、
その作業も速くなってきました。
この慣れるまでの間に、
私くらいの年齢の方々なら、
おそらく多くの方が挫折していると思います。
やはりこの年になってくると、
IT環境にアジャストしていくというのは
かなり困難なことなんですよ。
★「CANVAがうまく使えない」はただの「感想」
ではなぜ、私はこういったITやネット環境に、
四苦八苦しながらも、
なんとかついていくことができているのかということです。
負けん気と根性以外にも
もう一つ要因があります。
その一つというのが、
課題と対応策を「言語化」する力です。
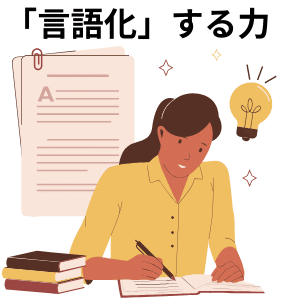
この半年間は、パソコンに向かいながら、
その「言語化」の繰り返しでした。
たとえば、CANVAがうまく使えない。
「うまく使えない」というのは、
感想であって、分析ではありません。
まず、どのような事象に対して
「うまく使えない」と考えているのか、
細分化します。
たとえば、CANVAはパワポとか
WordなどのWindowsソフトと違い、
常にデータが同期されるので、
データが消えてしまう心配はありません。
しかし、以前使ったデータが
探せなくなってしまうことがあったりしました。
つまり、私がCANVAを
「うまく使えない」と
感じている原因のひとつが、
「以前使ったデータが探しにくい」
ということだったのです。
これが課題の言語化です。
で、解決策も言語化します。
ネットで調べてみると、
似たようなことで悩んでいる人は
いるもので、
そこにはちゃんと解決策がありました。
言語化すると、
「CANVAで作ったコンテンツは、
CANVA内にフォルダを作成して、
そこに格納しておくこと」
これが解決策です。
★二流の教師が生き残るためのスキル
分析力、言語化を自慢しているように
聞こえるかもしれませんが、
そうではありません。
これは、教師として、二流三流だった私が、
なんとか教師として生き残るための、
習慣だったのです。
若い頃は学級経営が下手でしたので、
学級崩壊寸前にまでなったことがあります。
でもなんとか乗り切ったのは、
この習慣、つまり「言語化」だったのです。
言語化の良さは再現性にあります。
たとえば、私が6年生の国語を教える際、
「やまなし」という教材がありました。
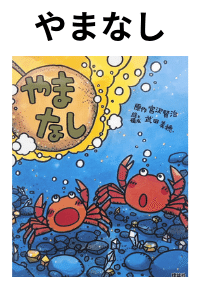
おそらくみなさんも
教えてもらった記憶はあるのではないでしょうか。
私は宮沢賢治が好きなんですが、
あの世界観を子どもたちに教えるとなると、
かなりの技量が必要です。
教師として二流、三流の私に、
この教材に太刀打ちできる力はありませんでした。
この作品は比喩表現や抽象的な表現が多く、
大人でもその解釈に戸惑ったりするはずです。
抽象画の解釈力と似ていています。
鑑賞の経験と技量が備わっていなければ、
ピカソの作品などを鑑賞しても、
人によっては落書きにしか見えないのと似ています。
「やまなし」はそんな教材でした。
★言語化と再現性
ただ、ある時、
「この川の深さはどれくらいなのかな」
という発問をしたことで、かなり議論が深まったのです。
一般的に、こうした文学作品において、
現実的な事象を問うことにあまり意味はありません。
しかし、子どもたちは
明らかに授業に乗ってきましたし、
少なくとも考えました。
その日の授業の振り返りは以下のとおりです。
「抽象的な教材の場合は、
まずは具体から考えさせ、
徐々に抽象へと思考を深めると
うまくいく場合があるのかもしれない」
「明日の授業では、少し抽象度を上げて
『あなたの考えるクラムボンとは何か』
について考えさせたい」
うまくいった要因を具体化し、
次はどうするのかまで言語化しています。
言語化することで、
経験が技術となり、知見となって
蓄積され再現性が担保されるのです。
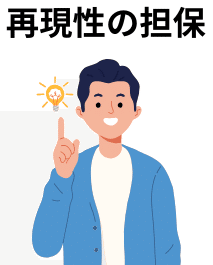
★マイナンバーカードで確定申告
このように、振り返りは
「言語化」してはじめて効果がある
ということに気づかされたのです。
やってみるとわかりますが、
良かった点や課題の分析が曖昧だと、
言語化できません。
時に挫けそうになることもありますが、
人生100年時代においては、
「学び続けること」が必須です。
で、「学び続けること」というのは、
この「言語化」だと思っています。
年齢のことを言っていても仕方がありません。
今後も、前面に立ちはだかる課題から
目を背けることなく、
「課題の言語化」と、
対応策の「言語化」で
乗り越えていきたいと思います。
と言いつつ、マイナンバーカードでの確定申告が
うまくいかなくて、
国に文句を言いたくなっている
自分がいて、情けない次第です(笑)。
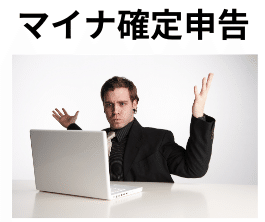
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/


